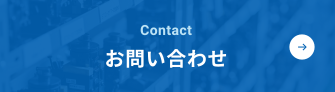近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波は、製造現場だけでなく、研究開発の現場にも押し寄せています。とくに、ロボットやAI、IoTなどの最新技術を活用し、実験・分析作業の自動化・効率化を図る「ラボラトリーオートメーション」は、多くの企業にとって、今後、発展が期待される課題となっています。
背景にあるのは、人手不足、熟練技術者の高齢化、そして、時間やコストの制約といった課題です。これらの課題を解決し、研究開発の効率を飛躍的に向上させる可能性を秘めているラボラトリーオートメーションは、まさに、これからの研究開発のあり方を変える可能性を秘めていると言えるでしょう。
ラボラトリーオートメーション導入による具体的なメリットや事例、そして、今後の展望について、オザワ科学の遠田と惣名、そして、ヤマト科学株式会社の大石氏が語り合いました。
#参加者
オザワ科学株式会社 遠田幸央
オザワ科学株式会社 惣名聡
ヤマト科学株式会社 ロボティックソリューション事業部 理事(部長) 大石保之氏
1.ラボを取り巻く現状と、加速する自動化の波

――近年、ラボラトリーオートメーションが注目されている背景と、各社の関わりについてお聞かせください。
遠田:私が担当しているユーザーでは、10年ほど前からラボの自動化の話が持ち上がっていて、5年ほど前からいよいよ本格的に検討が始まりました。人の手で行っていた作業を機械に置き換えていこうという流れになっており、これからが正念場だと感じています。
人件費削減がひとまずのゴールだと思われますが、現場では「とにかく自動化できるものはすべて自動化しよう」という機運が高まっています。実際に、私が提案している「LIMS(Laboratory Information Management System)」(※)も、近年引き合いが増えています。
(※)「LIMS」(Laboratory Information Management System)
実験データの記録、管理、分析などを一元的に行うことができるシステム。従来、実験データは紙媒体で管理されることが多く、データの検索や分析に時間を要し、人為的なミスが発生する可能性もあった。「LIMS」を導入することで、これらの課題を解決し、業務効率化とデータの信頼性向上を実現できる。

オザワ科学株式会社 遠田幸央
惣名:私の担当であるユーザーでも、とくに電池関連の研究開発現場では、事業拡大に伴い、スピードと効率性が強く求められています。そのため、「自動化」は常に話題の中心です。ただ、設備を導入すればそれで終わりではありません。メンテナンスや修理など、その後の運用まで見据えた計画が必要だと痛感しています。
大石:人手不足という点では、私も深刻さを増していると感じています。企業は、募集をかけても人が集まらず、とくに若い世代は地方の企業ほど敬遠する傾向があるようです。企業によっては、このままでは将来的に工場の操業停止も余儀なくされるのではないかと、危機感を募らせているケースもあります。

ヤマト科学株式会社 大石保之氏
そのため、人材不足を補うための設備投資や自動化への取り組みを、これまで以上に加速させていきたいという声も聞こえてきます。
また、人手不足と並んで、属人化による作業のばらつきもお客様からよく伺う課題です。同じ分析作業でも、担当者によって結果にばらつきが出てしまうという悩みは根深いですね。そこに自動化システムを導入することで、誰が作業しても一定の品質を保てるようになり、安定した結果を得ることが可能になります。
――製造現場では、以前からロボットによる自動化が進んでいます。製造現場と研究開発の自動化には、どのような違いがあるのでしょうか?
遠田:製造現場では、以前からロボットによる自動化が当たり前のように行われてきました。しかし、研究開発の現場では、自動化は遅れている状況です。これまで人の手で行う作業や判断が重要視されてきたからでしょう。しかし、ここにきてようやく、自動化に本腰を入れ始めたという段階です。

協同ロボットイメージ
大石:ロボット自体は以前からありましたが、大型で高価なものが多く、研究開発のラボのように限られた空間への設置は適していませんでした。しかし、近年は小型で安全性の高いロボットが登場したことで、ラボでも導入しやすくなっています。また、従来の産業用ロボットは安全柵が必要でしたが、最近では、人と一緒に作業ができる協働ロボットも普及してきています。このように、ロボット技術の進化は目覚ましく、ラボの自動化を後押しする大きな要因となっています。
2.ラボラトリーオートメーションの導入事例

オザワ科学株式会社 惣名聡
――実際にラボラトリーオートメーションを導入した事例をご紹介ください。
遠田:恒温水槽からオイルバスへサンプルを移すという作業を自動化した事例があります。人が一つずつ移動させていたのですが、ロボットを導入し、決められた時間ごとに自動で移動させるようにしました。
他にも、ピペットを使った前処理作業、たとえば希釈作業などをロボットで自動化する事例も出てきています。人が行うには単純作業でも、正確性が求められるため、ロボットによる自動化は効果的です。
惣名:真空乾燥機と真空ポンプを使った事例ですが、真空ポンプが稼働していないと、どうしても装置内部が錆びてしまうという問題がありました。そこで、タイマーで制御して定期的に大気を装置内に送り込むシステムを構築しました。
他にも、ロボットとインピーダンス測定装置を組み合わせた事例があります。従来は手作業で行っていた測定を自動化し、省力化を実現しました。

>>【導入事例】生菌数試験自動化システム|中外製薬工業株式会社様
大石:当社では製薬メーカー向けに、注射用水中の細菌の有無を検査する「生菌数試験」を自動化するシステムを納入した事例があります。まず、サンプル水をフィルターでろ過し、そのフィルターを培養器内の培地に貼り付けて培養します。そして、一定期間後に菌が増殖しているかどうかを確認するのですが、この一連の作業をロボットで自動化しました。
また、HPLCやICPなどの分析装置を使った検査の前処理工程を自動化するシステムも数多く手がけています。サンプルの溶解、ピペットによる移動、専用容器への注入といった作業を、ロボットがすべて自動で行うことで、人為的なミスを減らし、分析結果の精度向上に貢献しています。
――ラボラトリーオートメーションは、すでにさまざまな場面で導入が進んでいることがわかりました。現状で、自動化が難しい工程もあるのでしょうか?
遠田:粉体の秤量作業は自動化が難しい工程の一つです。液体と違って、粉体は流れ落ちにくいため、正確な重量を測定するのが困難です。

大石:たしかに、粉体のハンドリングは、多くの企業が頭を悩ませている課題の一つです。ヤマト科学でも、粉体自動秤量装置の開発に取り組んでいますが、粉体の種類や性状によって最適な方法が異なるため、汎用的なシステムを構築するのが難しいのが現状です。
惣名:他にもラボのさまざまな作業が自動化していくと思われますが、一方でコスト面も課題ですね。自動化には相応の費用がかかるため、コストに見合った成果が得られるかが問われます。
3.ラボの未来を創造する、AI・ロボット・遠隔化の可能性

――ラボラトリーオートメーションの未来について、どのように展望されていますか?
遠田:「AIによる分析」は、今後のラボラトリーオートメーションにおいて、重要なキーワードになると考えています。研究開発の現場では、日々、膨大な量のデータが生まれており、その解析に多くの時間と労力が割かれています。AIは、分析条件やプロセスの最適化において重要な役割を果たしていくと思われます。今後は人間に代わってAIが判断を下し、自律的な意思決定が自動化されることが期待されます。また、研究開発の分野では、複雑な条件を最適化するなどの判断も自動化されていくかもしれません。
「データの保管方法」も、今後ますます重要になってくるでしょう。先ほどお話したLIMSやクラウドなどを使って、実験データを一元管理し、必要なときに誰でも簡単にアクセスできる環境を整えることが重要です。それから、「遠隔化」も、ラボの未来を変える可能性を秘めた技術です。装置の稼働状況を遠隔で監視したり、遠隔地から装置を操作したりすることができれば、場所にとらわれずに研究開発を進めることができます。

惣名:私が担当しているユーザーでは、近年、CAE(Computer Aided Engineering)を使ったシミュレーションに力を入れています。従来は、実際に試作品を作って実験を繰り返していましたが、コンピューター上でシミュレーションを行うことで、開発期間の短縮やコスト削減を図っています。
CAEによって、ある程度の段階まで、試作品を作ることなく、実験計画を立てることができるようになってきています。また、コロナ禍以降、在宅勤務が増加したこともあり、ラボでもリモートワークを導入したいという要望が高まっています。VR(Virtual Reality)技術などの活用も話題に挙がりますが、実現には至っていない状況です。

大石:ヤマト科学では最近、創薬分野の自動化に力を入れています。とくに、抗がん剤など、人体に影響がある薬品の開発では、研究者が被爆するリスクを最小限に抑える必要があります。そこで、ロボットを使った自動化システムを導入することで、安全性を確保しながら、効率的に研究開発を進めることができるようになると考えています。
また、将来的には、AIを搭載したロボットが、実験データに基づいて、自動的に実験条件を調整したり、新たな実験を提案したりする時代が来るかもしれません。そうなれば、研究者の負担を大幅に軽減し、より創造的な研究に専念できる環境が実現すると期待しています。さらに、遠隔操作技術と組み合わせることで、自宅など、離れた場所からラボの装置を操作することも可能になります。そうなれば、研究者は、場所にとらわれず、より柔軟な働き方を選択できるようになると考えます。
4.ラボラトリーオートメーション普及への課題と展望

――ラボラトリーオートメーションは、未来への可能性に満ちている一方で、普及にはいくつかの課題もあるという話を聞きます。具体的には、どのような課題があるのでしょうか?
遠田:機器を連携させて自動化システムを構築する場合、それぞれの機器が持つ情報を共有する必要がありますが、メーカー側の情報開示が十分でないために、連携がうまくいかないケースもあると聞いています。
惣名:あとは、「導入後の運用」も課題です。高度な自動化システムを導入しても、ロボティクスやAI・プログラミングなどの知識がないと回せないんですよね。装置同士を連携させてほしいという要望があっても、知識不足で対応が難しいことがあります。
大石:人材育成も重要ですが、そもそも、ラボラトリーオートメーションに精通した人材が不足しているのが現状です。そして遠田様のお話にもありましたが、日本の分析機器メーカーは、海外メーカーに比べて、外部通信機能が搭載されていない装置が多いと感じています。外部通信機能がないと、他の装置と連携して自動化システムを構築することが難しくなります。
――グローバル競争が激化する中で、日本のラボが競争力を維持していくために大きな課題ですね。
大石:日本の分析機器メーカーも、危機感を持って、この課題に取り組む必要があると思います。幸いなことに、JAIMA(日本分析機器工業会)が中心となって、分析機器の通信規格の標準化に向けた取り組みが進められています。「LADS(Laboratory Automation Data Standard)」と呼ばれるこの規格が普及すれば、異なるメーカーの装置間でも、データのやり取りが容易になり、ラボラトリーオートメーションが大きく進展すると期待されています。
ラボを進化させる総合商社オザワ科学の役割

――最後に、ラボラトリーオートメーションの普及に向けて、各社どのような役割を果たしていきたいかをお聞かせください。
遠田:オザワ科学は長年、研究開発の現場に寄り添い、さまざまな機器や技術を提供してきました。ラボラトリーオートメーションにおいても、お客様のニーズを的確に捉え、最適なソリューションを提供していくことが、私たちの使命だと考えています。
まずは、お客様の課題やニーズをしっかりとヒアリングすることから始めます。その上で、最適な機器やシステムを提案し、導入から運用まで、しっかりとサポートさせていただきます。また私自身も、日々アップデートされるラボオートメーションに関する情報についてさらに勉強を重ね、お客様に最適な提案ができるよう努力していきたいと思っています。

惣名:そうですね。私たちは、特定のメーカーに縛られることなく、最適な機器やシステムを組み合わせることができるのが強みです。ヤマト科学さんのように優れた技術を持つメーカーと連携し、お客様に最適なソリューションを提供していきたいと考えています。そのためにも、メーカーの情報を収集するだけでなく、自分自身の知識も高めていかなければなりません。

大石:ラボの自動化を検討されているお客様は、どのように自動化すればいいのか、イメージがわかない方が多いと感じています。ヤマト科学としては、ラボラトリーオートメーションの導入事例を動画などで紹介することで、お客様に具体的なイメージを持っていただき、導入を検討するきっかけになればと考えています。
オザワ科学さんのような総合商社にも、そうした情報提供を通じて、ラボラトリーオートメーションの普及に貢献していただければ幸いです。